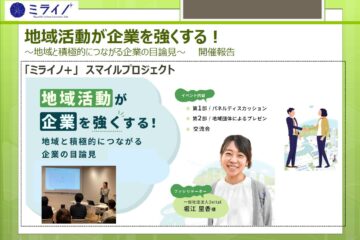三ツ星大学★★★ワイン編(1限目)
至高のグルメ講座『三ツ星大学★★★』
東広島が世界に誇る食の探究者が贈る至高のグルメ講座『三ツ星大学』、今回のテーマは歴史と伝統ある「ワイン」です!
「軽い酸味があり、ふくよかな香りが立ち上がる…」なんてワイン片手に開催できれば良かったのですが、今日は我慢がまん。日本ブドウ・ワイン学会の会長も務められ、ワインに深い見識をお持ちの後藤奈美さんを講師にお迎えしてワインの「香り」について教えていただきました。
講義はまず、後藤さんが理事長を務められる日本で唯一のお酒の研究所「酒類総合研究所」をご紹介いただき、ワインの作り方、そして香りの秘密へと続きます。

1限目◆2月6日(土)『香りで迫るワインの魅力!』
「この『香り』はどう感じますか?具体的に例えてみてください!」
う~ん、味と違って「匂い」は日常生活で言語化する場面って少ないですよね。「いざ言葉にしようと思うとできない…」参加者に共通する感想でした。
そんな香り、サインエスしていきましょう。

1. ワインの造り方
まずは、赤、白、ロゼの違いやワイン造りの基本を教えていただきました。
「白ワインは果汁を絞った後で、赤ワインは絞る前に発酵させます。」」
「発酵に用いる酵母、昔はブドウについていた自然のものでしたが今は品質を安定させるために市販の乾燥酵母を添加しています。」
「搾汁機も垂直型、水平型(バランス型、ブーハー型)など様々あります。」
「最近増えているスクリューキャップや合成コルクは、天然のコルクと比べてワインにカビ臭が付きにくいというメリットがあります。でもコルクがなくならないのは、抜く姿がカッコいいからかもしれませんね(笑)。」

2.ワインの香りの秘密
ソムリエのように気の利いた言葉でかっこよくワインの「香り」表現したいですよね。実はワインの香りを決める大きな要因はたったの2つです。
1つ目はブドウがもともと持つ香りです。
カベルネ・ソーヴィニヨンのグリーンな香り、シラーのコショウの香りなどなど、品種ごとにブドウが本来持っている香りがそのままワインの特徴になります。
2つ目は発酵や熟成によって生まれる香りです。
ブドウの状態では全く香らない「香りの素」が、発酵する過程で酵母によって切り離されることで人が感じる香りとなり、これがワインに独特の香りを添えます。
「ブドウも人にワインを作ってほしいから「いい香り」の素を持っているわけではなく、不要な成分を分解する過程でたまたま出来た成分が、ワイン作りにおいては人にとっていい香りに変わるのです。」
印象的なお話でした。意図せず新しいものが生まれて輝く、まさにイノベーション!

3.香り体験
3つのサンプルをご準備してみなさんに評価していただきました。
『リナロール』
「オレンジやレモンの爽やかな柑橘臭!」「葉っぱっぽい…かな」「森林の芳香剤みたい」
リナロエという木の精油がアロマテラピーに使われることが名前の由来の成分だといわれるこちらの香り、爽やかでフレッシュな印象を受けた方が多いようですね。
『3MH』
「汗臭い…」「中学生の汗の臭いみたい」「消毒液」「ちょっと目に染みる香り」
人によって感じ方が大きく変わる香りの1つです。ワインの教科書には「グレープフルーツ」とか「猫のおしっこ」と表現されているそうで、白ワインのソービニヨンブランの特徴的な香りです。言われてみるとグレープフルーツの香りのような気もしてきますね。
『β-イオノン』
「リンゴ」「緑茶」「スミレ」「バニラ」「ん?? 全然匂わない…」
この香りは葉緑体のカロテノイドを分解してできる成分ですが、実は1/4から1/2の人が感じることができない香りなんだそうです。人によって全く感じない香りがあるなんて驚きですね。藤田CFOは(元食品研究者なのに)全く匂いを感じずショックで…(笑)
いかがでしたでしょうか、アーカイブでは実際に香りを嗅いでいただくことができませんが、ぜひ今度ワインを召し上がる時に意識してみてください!

4.質疑応答
Q 「いい香り」の定義って何ですか?
難しい質問ですが、たくさんの人がいい香りと感じるものがいい香りだと思います。同じ香りの感じ方が「グレープフルーツ」と「汗」に分かれるなら、「グレープフルーツ」に感じる人が多い方がいい香りです。
Q ワインの審査員は本当にテイスティングだけで銘柄まで当てているのですか?
”ソムリエコンクールで優勝するような方”は本当に識別されています。まず品種を絞り、次に地域を絞り、最後に生産者や製造方法を想像して銘柄を識別されているようです。単純に味覚だけでなく、地域の特徴や生産者の生産方法等を知識として勉強しているから当てられているのだと考えています。
Q こういう(サンプルのような)成分を組み合わせたら、ワインの味や香りを再現できますか?
現在の技術では、ある程度近いところまではできても、その全てはとても再現できません。自然の力は凄いですね。
Q ヨーロッパで美味しいと評価されたワインが実は日本人の口には合わない人がいるのではないでしょうか?
ヨーロッパで美味しいとされる発酵バターの香りを日本人が苦手と感じる人が多いようなことがワインでもあります。あっさりした日本食には味の濃いワインが合いにくいということもありますよね。

編集後記
気づかれましたか?ミライノ+オリジナルワインボトル、藤田CFOの夜なべ自信作です。残念ながら非売品ですw